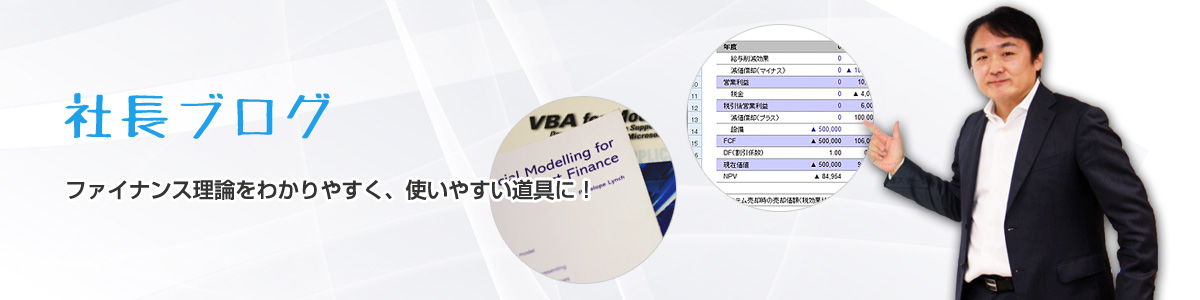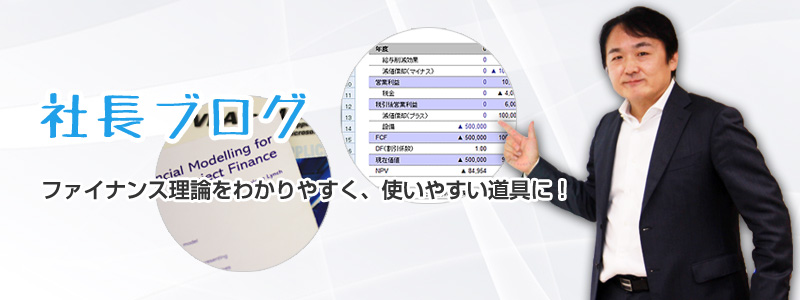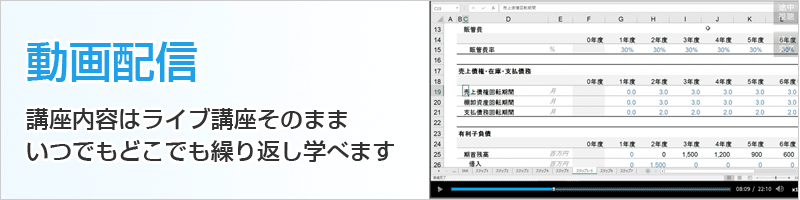日本の企業経営は、長らくPL(損益計算書)、つまり「どれだけ売上が上がったか」「どれだけ利益が出たか」という点ばかりが注目されてきたように感じます。もちろん、利益を出すことは企業活動の業績を評価する指標としてステークホルダーから注目されており、非常に重要です。
しかし、それだけでは、企業の「強さ」や「持続可能性」を測ることはできません。私は、これからの日本企業は、PL重視の経営からBS(貸借対照表)マネジメント重視の経営にシフトすべきと考えています。
BSマネジメントとは、単に資産を持てば良いという話ではありません。いかに効率的に資産を運用するか、事業に関係のない「非事業資産」を整理するか、あるいは長年の付き合いで保有している「政策保有株」をどう縮減していくか。こうした「資産の質」を高める取り組みが、企業価値を本質的に向上させる鍵となります。
そして、BSマネジメントの中でも特に即効性があり、企業の「血液」とも言えるキャッシュフローに直結するのが、「運転資本(Working Capital)」の管理です。運転資本とは、大まかに言えば「売掛金(未回収の売上)」と「在庫」から、「買掛金(未払いの仕入代金)」を差し引いたもの。これが多すぎると、たとえ黒字でも手元の現金が足りなくなる「黒字倒産」のリスクさえ抱えることになります。
実は、私自身もかつて日産自動車に在籍していた頃、この運転資本の管理に奔走した経験があります。当時はまさに経営再建の真っ只中。いかにして売掛金の回収を早めるか、いかにして無駄な在庫を適正化するか、そしてそれらによって生み出したキャッシュでいかに借入金を削減するか。まさにBSの「左側(資産)」と「右側(負債)」を同時に圧縮する仕事をしていました。
その過程で、非常に印象的な出来事がありました。私が所属していた財務部が「部品メーカーへの支払いを見直すべき(長期化すべき)」という提案をゴーン氏にしました。彼は、我々の提案を即座に却下しました。
彼の考えは、こうでした。「支払いを遅らせるな。むしろ早く支払ってやれ。その代わり、部品の価格を今より下げるよう交渉をしろ。」
支払いを遅らせれば、資金繰りに困った部品メーカー(サプライヤー)は、高い金利を払って銀行からお金を借りる必要が出てきます。そして、その支払利息分は、結局「部品の価格」に上乗せされて、巡り巡って我々(日産)が支払うことになる。これが彼の考えだったのです。
今回のブログで取り上げたいのは、まさに「買い手の信用力や資金力を活かして、サプライチェーン全体を最適化する」という「サプライチェーンファイナンス(SCF)」です。
具体的には、買い手企業(発注企業)の信用力を活用して、売り手企業(サプライヤー)の売掛債権を早期に現金化する仕組みを指します。例えば、代表的な手法の一つに「リバースファクタリング」があります。これは、買い手企業(発注企業)の信用力を背景に、金融機関がサプライヤーの持つ売掛債権を買い取り、サプライヤーに代金を早期支払いする仕組みです。
ある東京都の中堅金属建材メーカーの事例では、まさにこのリバースファクタリングを導入しました。目的は「取引先企業の資金繰り安定化」と「自社の支払業務の効率化」でした。結果として、サプライヤーは低いコストで早期に資金化できるようになり、買い手であるこのメーカーも、従来の手形発行・管理業務がなくなり、月20~30時間の業務圧縮と経理部門の人員1名削減(月額100万円超のコスト削減)を実現したのです。これは、単なる資金繰り支援に留まらず、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進にもつながる、見事な一手と言えます。参考:「サプライチェーン・ファイナンスを導入し、仕入先との協力関係を強化する企業」
そしてもう一つの手法が「ダイナミック・ディスカウント(早期支払い割引)」です。これは、買い手企業が「自社の余剰資金」を使って請求書の早期支払いを行い、その対価としてサプライヤーから日数に応じた「割引(ディスカウント)」を受け取るスキームです。例えば、ある大手自動車メーカーA社は、北米の子会社でこの仕組みを導入しました。狙いは、米国市場で余っていた自社の余剰資金(ドル)を有効活用しつつ、中小の現地サプライヤーへの支払いを早めることで、取引先支援と自社の利益改善(割引によるコスト削減)を両立することでした。この仕組みの素晴らしいところは、従来は金融機関経由のSCFが届きにくかった小規模なサプライヤーまで支援の輪を広げられる点です。買い手は余剰資金の運用利回りを向上させ、サプライヤーは資金繰りを改善することができます。参考:「Taulia ― FinTechを活用した「三方よし」の運転資金管理の仕掛け作り」
日本企業の経営は、今まさに転換点にあります。目先のPL(利益)を追うだけでなく、自社のBS(資産)を磨き上げ、特に運転資本の管理を徹底することが求められています。そして、その過程において、サプライチェーンファイナンス(SCF)は、自社の信用力や資金力という「見えざる資産」を有効活用し、取引先であるサプライヤーを支援しつつ、自社のコスト削減や業務効率化につなげられる、強力な「Win‑Win」のツールとなります。
こうしたファイナンスの知識や財務の視点は、もはや経理・財務部門だけの専門知識ではありません。これからのビジネスパーソンにとって必須の教養と言えるでしょう。もし、こうした「企業の血液」とも言えるキャッシュフローの管理や、企業価値を高めるための財務戦略について、もっと深く、実践的に学びたいと感じた方がいらっしゃいましたら、ぜひ「ファイナンス基礎講座」や「財務モデリング基礎講座」の門を叩いてみてください。