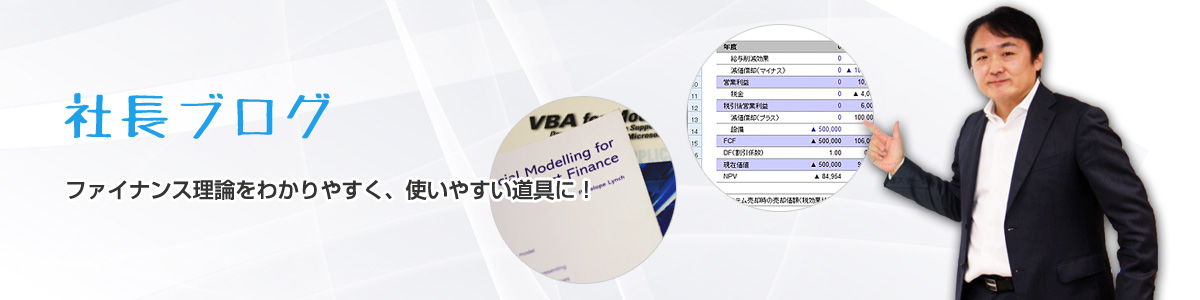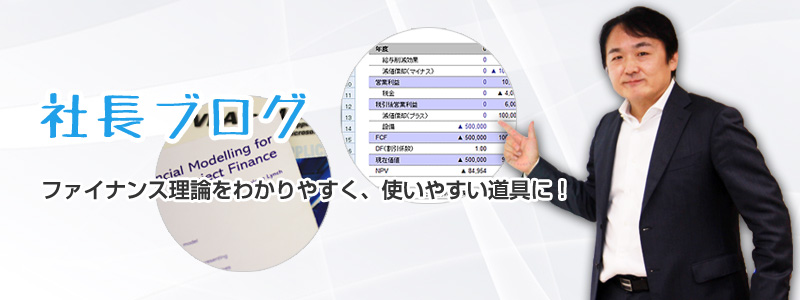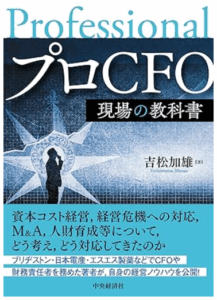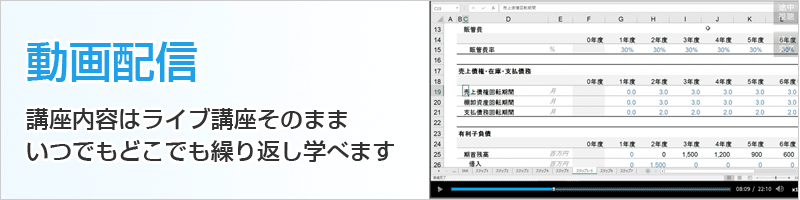変化の激しい時代、企業の舵取り役であるCFO(最高財務責任者)に求められる役割は、単なる「金庫番」ではありません。未来を予測し、企業価値を最大化へと導く戦略的パートナーとしての役割が、今まさに期待されています。
そんな中、ブリヂストンや日本電産(現ニデック)、エスエス製薬といった名だたる企業で、財務責任者やCFOを歴任した吉松加雄氏による『プロCFO 現場の教科書』は、まさに「現役CFO時代の筆者が欲しかったけれど、どこにもなかった本」という言葉通り、理論と実践が見事に融合した一冊でした。
本書の核心は、CFOの役割を「価値向上の軸」「組織体制の軸」「経営課題の軸」という3つの軸で立体的に捉え、持続的な企業価値向上を実現するための具体的な方法論を示している点にあります。しかし、私が特に素晴らしいと感じたのは、次の3つです。
1. 製造業出身ならではの「リアルな数字」の追求
私が素晴らしいと思ったのは、第7章「経営危機における企業変革」で紹介されている、直接原価計算(DC方式)を用いた業績シミュレーションです。コロナ禍という未曾有の危機において、売上が減少した際に利益がどう変動するのかを、変動費と固定費に分けてシミュレーションする具体例は、まさに類書にはないものです。
これは、製造業の現場を知り尽くした著者だからこその視点でしょう。類書が貸借対照表(BS)や損益計算書(PL)の一般的な分析に留まる中、コスト構造にまで踏み込み、「もし明日、売上が半減したら、どう手を打つべきか?」という経営者の切実な問いにどのように答えるべきか、一つの答えを導き出しています。
2. 今日から使える「実践ツール」の提供
本書が単なる「教科書」で終わらない最大の理由は、テーマによって設けられた「ワークショップ」の存在です。
例えば、第一章では「自社版CFO機能の高度化と効率化のビジョンモデルを作成する」といったテーマで、自社の状況を当てはめて考えるためのフレームワークが提供されています。さらに、これらのテンプレートは中央経済社のウェブサイトからダウンロード可能なため、読んだその日から自社で活用できるのです。知識をインプットするだけでなく、実践的なアウトプットに繋げるためのハードルを低くしてくれている点は、とても良心的です。
3. 一人のビジネスパーソンの歩みがわかるコラム
また、本書の随所に散りばめられた「コラム」や「プチコラム」が、専門書でありながら非常に興味深く、読み物としての面白さを加えています。
ここに書かれているのは、著者が若き日に先輩や上司から得た教え、サン・マイクロシステムズ時代に学んだことなど、豊富なビジネス経験から得られた「気づき」や「学び」のエピソードです。「BPRで月次決算『実働1日』の実現!」といった具体的な成功体験もさることながら、一人のプロフェッショナルがどのように知見を積み上げてきたのか、その過程が描かれています。
帯には、「こんな方にこそ読んでほしい」とあります。
* 経営力向上に取り組む企業経営者の方
* 現在CFO、もしくは将来CFOを目指している方
* 経営管理の高度化に悩んでいるマネージャー層の方
* M&AやPMIを成功に導きたいと考えている担当者の方
* これからの時代に求められるファイナンス人財の育成方法を知りたい方
* DXを活用して財務・経理業務を効率化したいと考えている方
この本は、あなたの会社が直面している課題解決のための教科書となるでしょう。