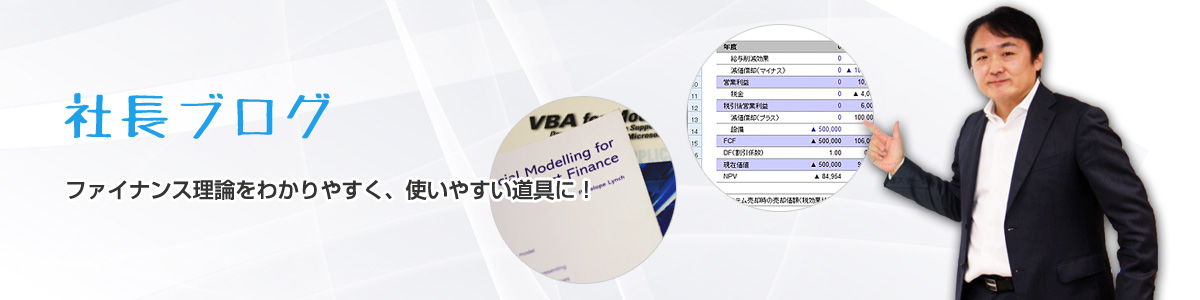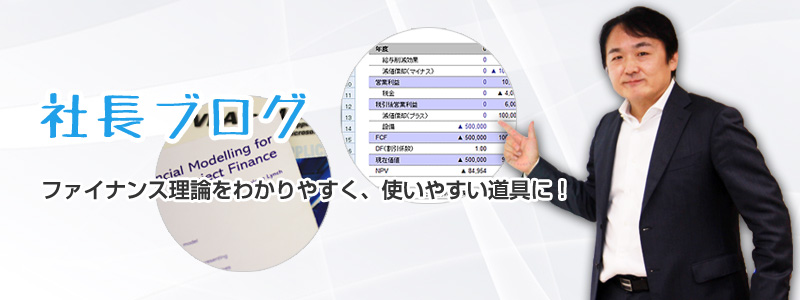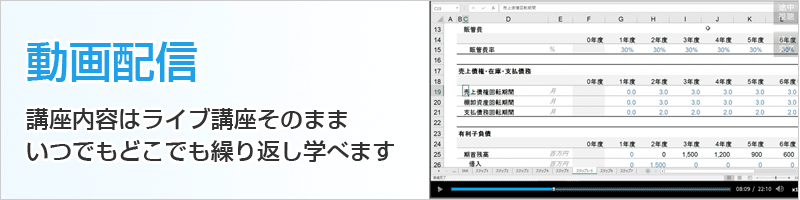もしあなたが会社の経営者で、新しい事業に投資するかどうかを判断する立場だったら、何を基準に決めますか?「儲かりそうだから」という感覚だけでは、大きな失敗につながるかもしれません。
実は、投資の世界には「この事業なら、最低でもこれくらいは儲からないと割に合わない」という明確な「ものさし」が存在します。これをハードルレート(割引率)と呼びます。
しかし、ここで一つ大きな落とし穴があります。例えば、あなたの会社が安定的な食品事業と、急成長中だけれどリスクも高いAI事業の二つを運営しているとしましょう。この性質が全く違う二つの事業に、会社全体の平均的な「ものさし(全社WACC)」を当てはめてしまったら、どうなるでしょうか?
会社全体の平均的なものさし(全社WACC)を使うと、リスクの高いAI事業への投資判断は甘くなりすぎ、「本当はダメなのにGOサイン」を出してしまうかもしれません。逆に、安定的な食品事業には厳しすぎるものさしとなり、「確実なキャッシュフローが見込めるのに見送り」という判断ミスにつながりかねないのです。これでは、会社の大切な資源を誤った場所に投下し、成長の機会を逃してしまいます。
だからこそ、事業のリスクに見合った、個別の「ものさし」を設定することが不可欠なのです。
では、その「ものさし」はどうやって作るのでしょうか?鍵を握るのは、資金提供者である株主と債権者(銀行など)が要求する収益率を、加重平均した事業別WACC(ワック:加重平均資本コスト)です。今回は、その計算プロセスを少しだけ覗いてみましょう。
WACCを構成する要素の一つが、株主が要求するリターン、すなわち株主資本コストです。これを計算する上で重要なのがβ(ベータ)という指標で、市場全体の動きに対して、その企業の株価がどれくらい敏感に反応するかを示します。しかし、企業の株価データから算出されるβは、その企業が抱える借金(有利子負債)の影響を受けた「レバードβ」です。
これは言ば、重い荷物(借金)を背負って走っている時の選手のタイムのようなもの。一方、その荷物の影響を取り除き、選手本来の実力、つまり事業そのものが持つリスクだけを測ったタイムが「アンレバードβ」です。事業の本当の実力を知るためには、一度荷物を降ろしてあげる必要があります。※レバードβとアンレバードβの関係式は、こちらのブログを参照してください
この図は、X事業の株主資本コストを実際に計算したものです。まず、A社からF社といったライバル企業たちのデータを集め、それぞれの「荷物(借金)」を一旦降ろして(アンレバード化して)、事業本来のリスク(アンレバードβ)を求めます。その平均値が0.51となりました。これがX事業の素の実力です。
次に、このX事業が背負う予定の荷物(D/Eレシオ0.87)を再び背負わせてあげる(リレバードする)ことで、レバードβは0.94と計算されます。最終的に、このレバードβを使ってCAPM(キャップエム)というモデルを使うと、株主資本コストは5.91%と弾き出されました。
さて、ハードルレート(事業別WACC)を構成するもう一つの要素が、銀行などの債権者が要求するリターンである負債コストです。これは、全社の負債コストを使えばいいでしょう。この負債コストは、借入金の利率から、利息を支払うことで得られる節税効果を差し引いて計算します。
X事業の株主資本コスト(5.91%)、税引後の負債コスト(仮に1.4%とします)、そして資本構成(D/Eレシオ=0.87)の3つを組み合わせることで、最終的な「ものさし」であるハードルレート(事業別WACC)が計算できます。この例では、X事業が乗り越えるべきハードルは3.81%となりました。
一見複雑に見えますが、このようにステップを踏んでいけば、誰でも論理的に最適なハードルレートを導き出すことができます。
このように、事業のリスクを正しく見極め、適切な「ものさし」を持つことが、企業の未来を左右します。「理論はわかったけど、実際に自分の手でExcelを使いこなし、企業の価値を算出できるようになりたい」「実践的な財務モデリングのスキルを身につけたい」と感じたなら、ファイナンス基礎講座や財務モデリング基礎講座が、あなたの強力な武器になるはずです。次の一歩を、ぜひ一緒に踏み出しましょう。