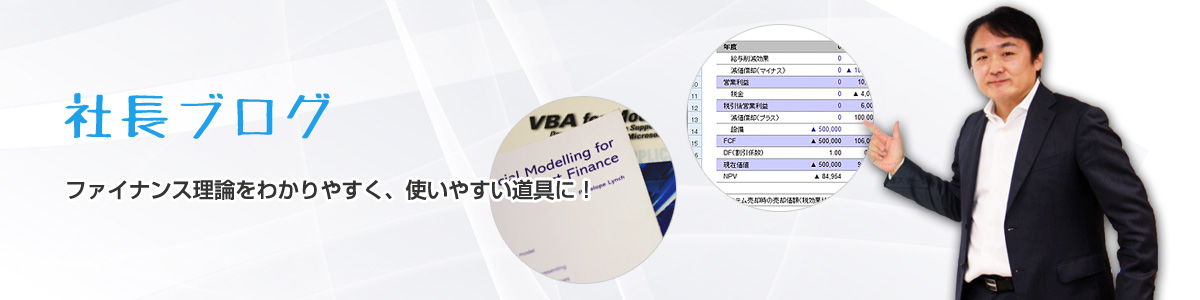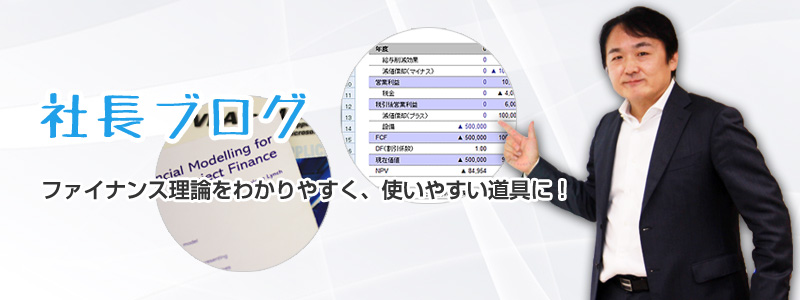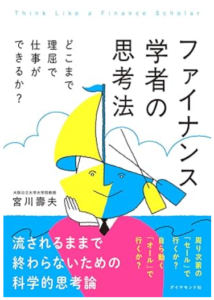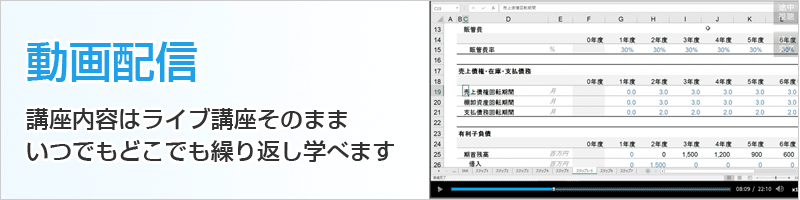今回のブログは、宮川壽夫先生の著書『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』を取り上げたいと思います。
宮川先生は、金融やコンサルティングの第一線で30年間実務を積み上げた後、50歳で大学教員に転身されたという、極めてユニークな経歴を持つ方です。実務とアカデミア、両方の世界を深く知るからこそ、先生の言葉には現場のリアリティと理論の鋭さが見事に同居しています。私自身、理論と実務を橋渡しする存在を目指してきたので、宮川先生の著書のファンでもありました。
・「新解釈 コーポレートファイナンス理論――「企業価値を拡大すべき」って本当ですか?」
・「企業価値の神秘」
実務の現場で「まずは実践」を重視し、理論の深掘りを後回しにしがちだった私にとって、これら二冊は、ファイナンス理論が持つ計り知れない「奥行き」と「骨太さ」を、改めて気づかせてくれるものでした。
宮川先生は本書「ファイナンス学者の思考法」の中で、ある若きCFOとのやりとりを紹介しています。配当政策を取締役会に提案するため、彼は上場企業の配当政策を徹底的に調査し、同業他社と比較し、証券会社の協力も得て、精緻な資料を作り上げました。ところが、宮川先生に、内容の説明を終えた彼は、どこか苦い顔をしてこう漏らします。「こういうことで本当にいいのかなと自信がないんですよ。なにか足りない考えはないでしょうか?」
このCFOの言動に、私はかつての自分自身の姿を重ねました。情報を集め、比較し、ベストプラクティスをなぞる。その努力自体は間違ってはいません。しかし、それはあくまで「作業」であり、「探究」ではない。目の前の資料を揃える前に、本来立ち返るべき問いがあるのではないか。宮川先生はCFOに、こう問いかけます。「貴社はなぜ株主に配当を支払いたいと考えているのか」「なぜ配当政策には目標が必要なのか」
宮川先生自身も大学院時代、配当政策を研究していた際、指導教授に「そもそも配当とは何のためにあるのか」と問われ、答えに詰まった経験があったことを告白しています。このような、実務の現場では「面倒臭い」とされる根本的な問いに向き合わなければ、どんな立派な数値目標も意味を持たないことを、宮川先生は今になって理解できると吐露しています。
ビジネスの現場では、喫緊の課題に追われるあまり、つい「他社がこうしているから」「平均がこうだから」といった理由付けで進めてしまいがちです。けれども、本当に重要な局面では、「そもそも、なぜ?」と敢えて立ち止まり、問い直す勇気が必要だと、この本は教えてくれます。たとえ周囲に「そんなこと考えてる暇があるのか」と笑われても、そのクリティカルな質問を投げかけることこそが、最終的に組織の進むべき道を正しく導くことにつながると言っているのです。
ファイナンスの研修講師として、私は受講生にファイナンスの知識を教えるだけでは足りないと常々感じていました。受講生の皆さん自身が問いを立て、考え、答えを探す力を持たなければ、本当の意味で学んだことにはならない。ただ、その前に、私こそが自分自身のファイナンスへの向き合い方を変える必要があると本書を読みながら、改めてその思いを強くしました。
ファイナンスを学ぶとは、単に理論を知ることではありません。世界を、企業を、そして自分自身を、より深く理解しようとする探究の旅に出ることなのだと思いました。そして、その出発点は、いつも「そもそも、なぜ~なのか?」というシンプルでありながら根源的な問いがあります。この本は、すべてのビジネスパーソンに読んでもらいたい一冊です。