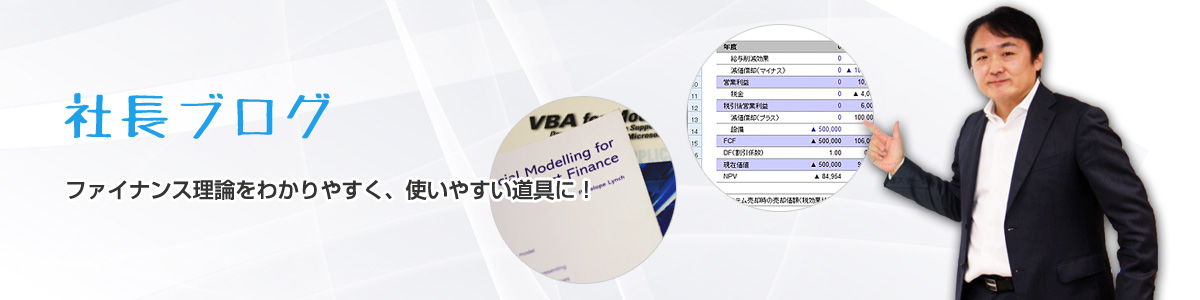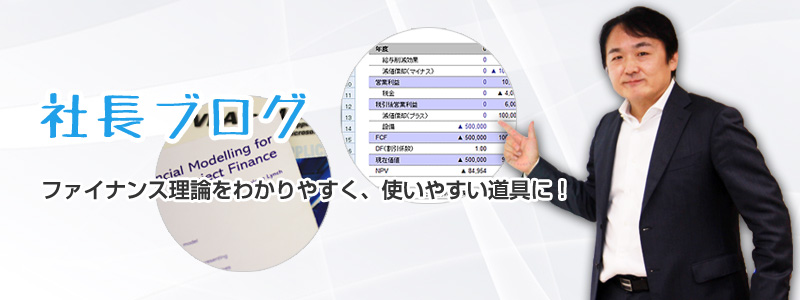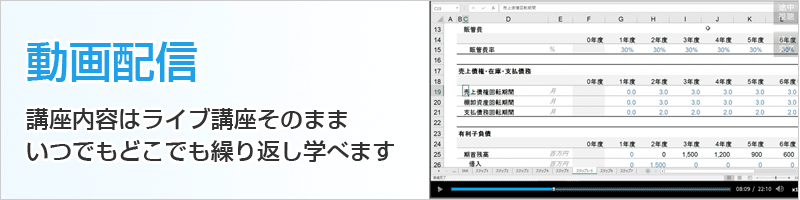2026年春頃の施行が予定されている「事業性融資の推進等に関する法律」。この法律の中核をなすのが、日本の金融慣行を根底から変える可能性を秘めた「企業価値担保融資(Enterprise Value Lending、以下EVL)」です。
長年にわたり、日本の融資は不動産担保と経営者の個人保証に大きく依存してきました。しかし、この伝統的なモデルは、知的財産やブランド価値といった「無形資産」を価値の源泉とする現代の企業、特にスタートアップなどにとって、大きな資金調達の壁となっていました。
今回は、この新たな金融のフロンティアであるEVLが、どのような仕組みで、企業にどのような可能性をもたらすのか、その全体像を分かりやすく解説します。
なぜ今、EVLが必要なのか?~日本の構造課題への処方箋~
金融庁がこの改革を強力に推し進める背景には、従来の融資モデルが日本経済のダイナミズムを阻害しているという強い危機感があります。
1.アセットライト企業の資金調達難: 有形資産を持たないスタートアップやテクノロジー企業は、融資の土俵に上がることさえ困難でした。
2.事業承継の障壁: 後継者が先代経営者の個人保証を引き継ぐという重い負担が、円滑な事業承継を妨げる大きな要因となってきました。
3.リスクテイクの抑制: 経営者個人が過大なリスクを負うため、企業の成長に不可欠な大胆な投資が抑制される傾向にありました。
金融庁は2003年にも「リレーションシップバンキングの機能強化」を掲げ、不動産担保・個人保証への過度な依存からの脱却を促しましたが、20年が経過しても根本的な解決には至りませんでした。この根深い慣行を転換するには、より強力な制度的介入が必要であるとの認識が、今回の法改正の直接的な引き金となったのです。
「企業価値担保融資(EVL)」のメカニズム
EVLは、従来の融資とは全く異なる発想に基づいています。その特徴的な仕組みを3つのポイントで見ていきましょう。
1.担保対象:「個別の資産」から「事業全体」へ
EVLの最大の特徴は、企業の「総財産」を一体として包括的に担保の対象とすることです。これには、不動産や在庫といった有形資産だけでなく、これまで担保として評価されにくかった知的財産、ブランド、顧客基盤、ノウハウといった無形資産も含まれます。融資の評価軸が、過去の実績や資産から、企業の将来性、すなわち「事業性」そのものへとシフトするのです。
2.実行の仕組み:「信託会社」の介在と「経営者保証」の原則禁止
この強力な担保権は、融資を行う金融機関が直接保有するわけではありません。濫用を防ぎ、専門的かつ公正な管理を確保するため、新たに認可された「企業価値担保権信託会社」が信託契約を通じて設定・保有します。さらに、本制度の活用にあたっては、日本の融資慣行の象徴ともいえる経営者保証が原則として禁止されます。これにより、経営者は個人資産と法人経営を切り離し、健全なリスクテイクに集中することが可能になります。
3.実行時:事業価値の維持を最優先
万が一、債務不履行に陥った場合でも、事業価値の維持が最優先されます。従来の担保実行が資産の切り売りによる価値の毀損を招きがちだったのに対し、EVLでは原則として事業譲渡(M&A)によって実行されます。その際、事業継続に必要な費用は優先的に弁済され、事業の「生きた価値」を損なうことなく、再生が図られます。
企業にとっての期待と新たな可能性
この制度は、特に以下のような課題を抱える企業にとって、大きなチャンスとなり得ます。
1.成長資金を求めるスタートアップ: 有形資産に乏しくても、将来性や技術力を評価され、エクイティ(株式)の希薄化を伴わずに大規模な資金調達を行う道が開かれます。
2.事業承継を控える企業: 後継者は個人保証の重荷から解放され、スムーズなバトンタッチが実現しやすくなります。
3.銀行との新たな関係構築: 企業側の34.4%が、EVLを機に銀行との関係がより協力的な「パートナーシップ」へと深化することを期待しています。自社の事業戦略を深く理解する「伴走支援」を受けられる可能性が生まれます。
企業価値担保融資(EVL)は、企業の真の価値である「事業性」に着目し、成長と挑戦を後押しする画期的なポテンシャルを秘めています。特に、これまで資金調達に悩んできたスタートアップや、事業承継という大きな課題に直面する中小企業にとって、新たな活路を開く強力なツールとなるでしょう。
しかし、この制度が成功するかは未知数です。金融機関が本当に企業の将来性を見抜く「目利き力」を習得できるのか、そして多くの企業が懸念する「評価の曖昧さ」や「経営への過剰な干渉」といった課題を乗り越えることができるのか。
次回のブログでは、今回ご紹介した「光」の側面だけでなく、この制度の構造的な欠陥やリスク、すなわち「影」の側面に深く切り込んでいきたいと思います。