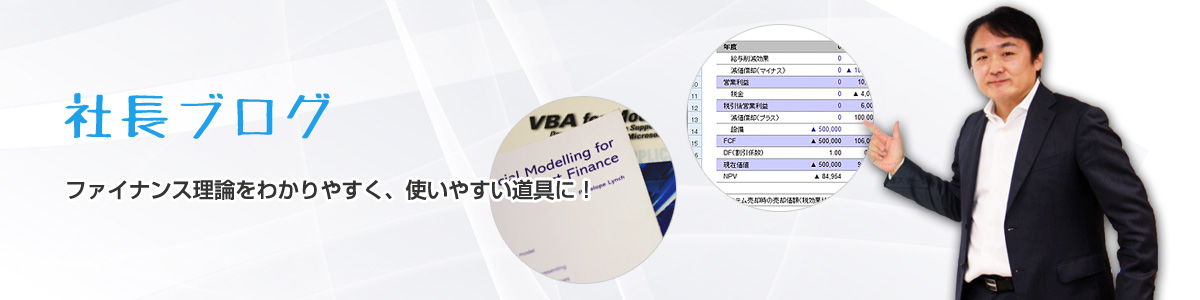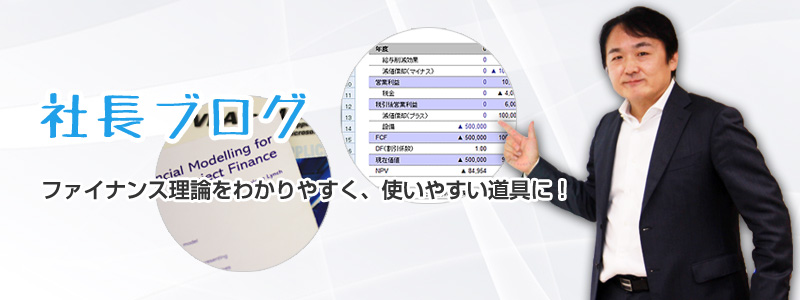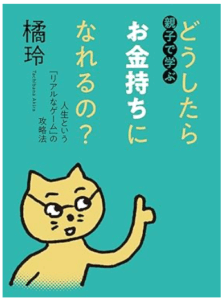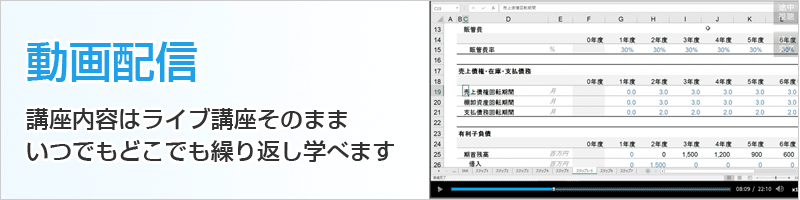子供の将来の幸せのために、親として何を教えるべきでしょうか。
昨今、「金融教育」が話題ですが、小学生に株の話をしても、それが本当に子どものためになるのか疑問に思う方も多いかもしれません。勉強やスポーツはもちろん大切ですが、変化の激しいこれからの社会を生き抜くために、もっと根本的に必要な「知恵」があるのではないでしょうか。
ベストセラー作家の橘玲が、その「答え」を解説した一冊が『親子で学ぶ-どうしたらお金持ちになれるの?』です。
本書は、小学生高学年から中学生でも理解できるように書かれており、単なるお金儲けのテクニックではなく、子どもたちが「人生というリアルなゲーム」を攻略するために本当に役立つ「考え方」を教えてくれます。
この本が生まれるきっかけとなった、私たち大人にとっても耳の痛いエピソードからご紹介しましょう。
衝撃のエピソード:「いいか、あんな大人になるんじゃないぞ」
本書の「はしがき」には、橘氏が近所のスーパーで体験した出来事が書かれています。
ある日、スーパーでは自動レジに長い列ができているのに、店員がいる対面レジには誰も並んでいませんでした。橘氏が空いている対面レジで精算していると、小学生の男の子を連れた父親が後ろに並びました。
おしゃれなジャケットを着たその父親は、自動レジの長い列に目をやると、子どもにこう言い放ったのです。
「いいか、あんな大人になるんじゃないぞ」
この言葉、みなさんはどう思いますか。
空いているレジがあるのに、なぜ大人たちはわざわざ混んでいる方に並ぶのか。おそらく、「みんなが並んでいるから」「いつもこっちだから」といった理由で、深く考えずに行動してしまったのでしょう。
この父親が子どもに伝えたかったのは、「周りに流されず、自分で状況を見て、最適な方法を判断しなさい」ということです。このエピソードこそが、本書の核となるテーマ、「合理的に考える」ことの重要性を象徴しています。
成功の鍵は「合理的に考える」こと
橘氏は、本書で解説しているような考え方を理解できたのは、自身が30代半ばを過ぎてからだったと正直に告白しています。それまでは、「好きなことをやっていれば、なんとかなるだろう」と思っていたそうです。
しかし、橘氏は社会で成功している人たちには共通点があることに気づきます。
「成功しているひとはみな、多かれ少なかれ、共通の考え方をしていることに気づきました。それをひと言でいえば、『合理的に考える』になるでしょう。」
なぜ、「合理的」に考えることが成功につながるのでしょうか?
それは、私たちが生きている資本主義社会(市場経済)が、合理的に考えるひとがお金持ちになるような仕組みになっているからだと橘氏はいいます。
「1+1=2」という当たり前ができない大人たち
では、「合理的」とは具体的に何でしょうか。難しく聞こえますが、橘氏は極めてシンプルに説明しています。
「経済合理性というのは、ものすごく簡単にいうと、1+1=2ということです。」
「当たり前ではないか」と思われるかもしれません。しかし、驚くべきことに、大人になればなるほど、この当たり前の事実を受け入れられなくなる人が増えていきます。
「大人になると、1+1は3だとか、極端な場合は100になると思っているひとがたくさんいることに気づくでしょう。」
例えば、「絶対に儲かる」という甘い投資話に飛びついたり、根拠のない精神論で「努力すれば必ず報われる」と信じて非効率なやり方を続けたりすること。これらは「1+1=100」になるという幻想を信じている状態です。
そして、市場経済の現実は残酷です。
「市場経済の残酷な世界では、1+1=2だという現実をちゃんと受け入れることができないひとは、カモとしていいように扱われ、失敗を繰り返し、なにもかもうまくいかなくなって、いつのまにか消えていくのです。」
逆に言えば、「1+1=2」という当たり前の事実を冷静に受け止め、それに基づいて未来を設計できるだけで、そうでない大多数の人々に大きな差をつけることができます。この知識を子どもが10代のうちから持っていたら、どれほど強力なアドバンテージになるでしょうか。
「他人と同じように長い列に並ぶ人生」にしないために
橘氏は、スーパーのレジ以外にも、合理的ではない人々の行動を挙げています。
深夜の空港で、係員が「タクシーは来ません。自分で手配してください」と叫んでいるのに、タクシー乗り場の長い列から動こうとしない人々。彼らは、自分でタクシー会社に電話するという「合理的な行動」を取らず、ただ思考停止して待ち続けます。
もし、私たちの子どもが、この「合理的に考える」という知識を今、手に入れたらどうでしょうか。
もちろん、それだけで成功が約束されるわけではありません。しかし、橘氏はこう約束しています。
「ただ、『他人と同じように長い列に並ぶ人生』にはならないことは約束できます。」
なぜ「合理性」が最強の武器になるのか?
本書をひと言でまとめるなら、「あとがき」にあるこの言葉に尽きます。
「人間は合理的ではないからこそ、合理性が大きな武器になる」
私たち人間は、感情的で、思い込みや周りの空気に流されやすい生き物です。だからこそ、多くの人が非合理的な行動をとってしまいます(例えば、空いているレジがあるのに、混んでいるレジに並ぶように)。
みんなが感情や雰囲気に流されている中で、自分だけが冷静に「1+1=2」と考え、合理的な判断を下すことができれば、それは非常に強力な武器になります。
「子どもにこんなことを教えると、冷たい人間になるのではないか」と心配する方もいるかもしれません。しかし、橘氏はこう述べています。
「でも、そんなことはありません。ロボットのような人生になんの意味もないことくらい、子どもだってわかります。それに、愛ややさしさは親であるあなたが態度で示すべきことで、本を読んで子どもに教えるようなものではないのです。」
愛や優しさは家庭で育み、社会を生き抜くための「合理性」という武器を与える。これこそが、現代における最良の教育の一つではないでしょうか。
本書は、親子でゲームをしながら楽しく学べる構成になっています。ぜひ一度、手に取ってみてください。