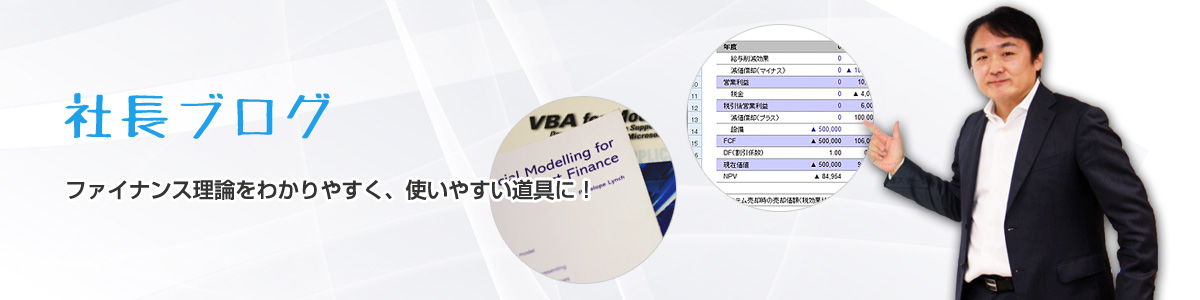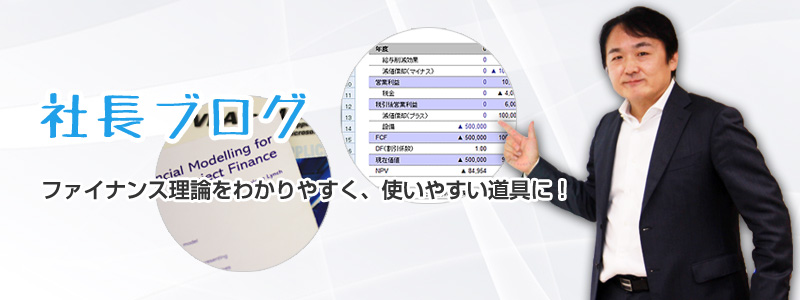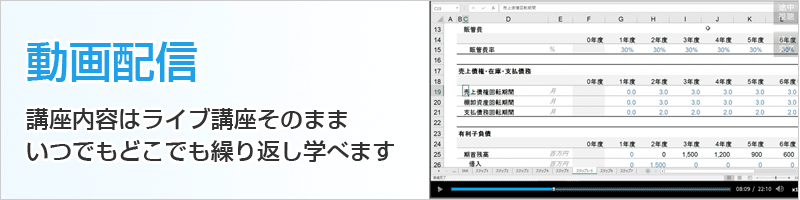「年利24%の配当」「元本保証で高利回り」。後を絶たない大規模な投資詐欺のニュースに、心を痛めている方も多いのではないでしょうか。最近あったフィリピンでの高利回り社債を謳った詐欺事件もそうですが、その手口は巧妙化し、多くの人が大切な資産を失う悲劇が繰り返されています。
「なぜこれほどまでに多くの人が、一見して非現実的な話に惹かれてしまうのでしょうか」
結論から言えば、金融詐欺の根底にあるのは、技術や金融商品の複雑さだけではありません。それは、人間の普遍的な心理を巧みに利用する、時代を超えて変わらない原理に基づいているからです。今回のブログでは、なぜ私たちが騙されてしまうのか、そして、どうすれば自分自身と大切な資産を守れるのかについて、考えてみたいと思います。
大原則1:忘れてはならない「リスクとリターン」の鉄則
まず、すべての投資の根幹にある大原則を再確認しましょう。それは「高いリターンの背後には、高いリスクがある」という、至極単純な事実です。
市場平均を大幅に上回るリターンを、「安全に」「元本保証で」得られる方法など、この世のどこにも存在しません。「うまい話には裏がある」とは、まさにこのことです。詐欺師が提示する「年利20%超」といった驚異的な数字は、その裏に「投資したお金がすべて無くなるかもしれない」という、極めて高いリスクが隠されている(あるいは、そもそも利益を生み出す仕組みが存在しない)ことを示す、危険なサインなのです。
大原則2:「成功者」の影に隠された多数の敗者 ― サバイバルバイアスの罠
「私の知人はこれで儲かっている」「こんなに多くの人が参加している」
これもまた、詐欺師が好んで使う手口です。私たちは、成功事例や「生き残った人(サバイバー)」の話に強く影響される「サバイバルバイアス」という認知の歪みを抱えています。
私たちは成功談から学ぶことの危うさをもっと知るべきです。ポンジ・スキームの初期段階では、実際に配当金が支払われるため、「成功者」が人為的に作り出されます。私たちはそのキラキラした部分だけを見て、「自分もそうなりたい」と願ってしまうのです。
しかし、その裏には、いずれ破綻する運命にある仕組みと、将来の被害者たちが無数に控えています。「みんながやっているから安心」は、思考停止の第一歩だと心に刻むべきです。
厳しい現実:金融のプロでさえ騙される
「自分は金融に詳しいから大丈夫」。そう思っている方ほど、注意が必要かもしれません。なぜなら、金融詐欺の被害は、専門家や大企業にまで及んでいるからです。
史上最大級の詐欺事件と言われるバーナード・マードフ事件があります。犯人は元NASDAQ会長という、金融界の権威そのものでした。その絶大な信用を悪用し、彼は世界中のプロの投資家や金融機関を欺き続けました。これは、特定のコミュニティ内の信頼関係を悪用する「アフィニティ詐欺」の典型であり、「あの専門家が言うなら間違いない」という権威への信頼がいかに危険かを物語っています。
日本でも、不動産のプロであるはずの大手住宅メーカーが「地面師」集団に騙された事件は記憶に新しいでしょう。これらの事件は、詐欺の被害者が必ずしも情報弱者だけではないという、厳しい現実を私たちに突きつけます。専門知識があることと、詐欺を見抜けることは、決してイコールではないのです。過信こそが、最大の敵となります。
【実践】資産を守るための思考チェックリスト
では、具体的に私たちはどう行動すれば良いのでしょうか。以下の思考のチェックリストを、ぜひ習慣にしてください。
1.「あり得ない」と疑う感性を磨く
市場を理解し、平均的なリターンを知っておくことが重要です。それを大きく逸脱する話は、まず疑ってかかる。その冷静さが第一の防御壁となります。
2.「何で儲けているのか」を自分の言葉で説明できるか?
「和牛オーナー制度」が、実は新規の出資金を配当に回すだけの自転車操業だったように、詐欺は一見もっともらしい「儲けの仕組み」を語ります。「和牛」や「金(ゴールド)」といった実物資産への投資に見せかける手口は、豊田商事事件の時代から繰り返される典型的なパターンです。そのビジネスモデルを、あなたがご自身の言葉で第三者に理路整然と説明できなければ、絶対にお金を出してはいけません。
3.相手は「何者」か?必ず裏を取る
金融商品を販売するには、金融商品取引業の登録が必須です。金融庁のウェブサイトで登録業者かどうかを検索するのは、数分でできる最も基本的な自己防衛であり、相手の素性を必ず確認する第一歩です。また、豊田商事事件のような大規模な詐欺事件を教訓に、クーリング・オフ制度といった消費者保護の仕組みも整備されました。こうした制度の存在を知っておくことも、いざという時に自分を守る力になります。
4.利害関係のない第三者に相談する
お金を出す前に、勧誘してきた本人や、その紹介者ではない、全く利害関係のない家族や信頼できる専門家に話してみましょう。一歩引いて、客観的な意見を聞くことは、私たちの判断を正常に戻す助けとなります。
最後に
金融リテラシーとは、単にお金を増やすための知識ではありません。それは、変化し続ける社会の中で、自分自身と家族の資産を悪意ある攻撃から守るための「鎧」なのです。
過去の無数の事件から学ぶべきは、手口の変遷ではなく、その根底にある「人間の普遍的な脆弱性」です。その脆弱性は、私を含め、誰もが持っています。だからこそ、私たちは常に謙虚に学び続け、冷静な判断力を養う必要があるのです。
私が提供するファイナンス研修も、まさにこうした「守りの知性」を鍛えることを目的の一つとしています。この記事が、皆さんの資産を守るための一助となれば幸いです。