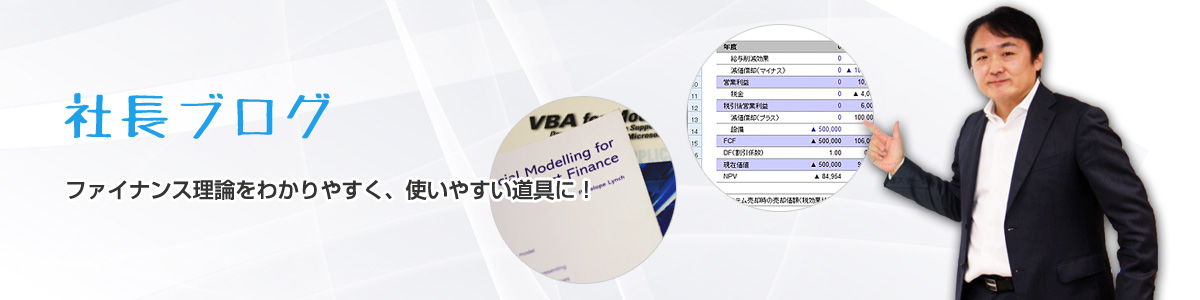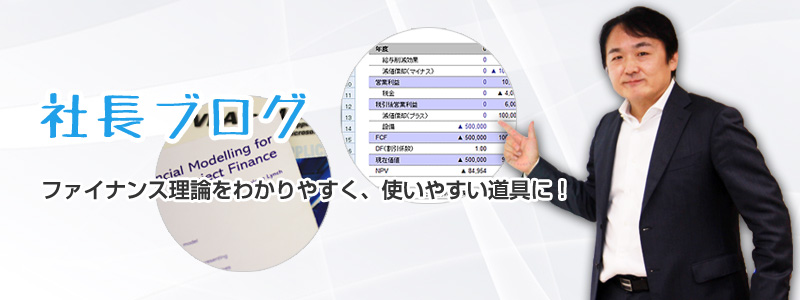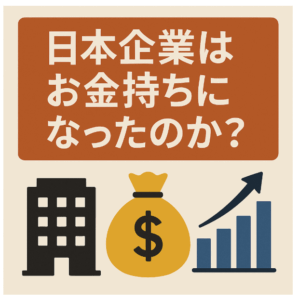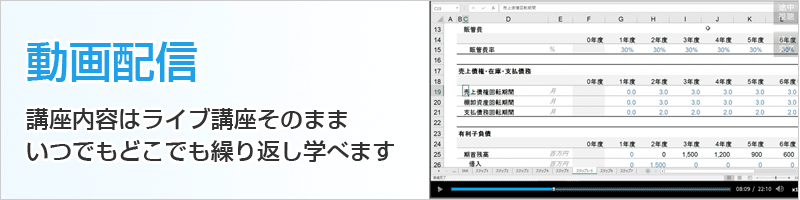コーポレートファイナンスの世界的権威であるアスワス・ダモダラン教授は、企業の現金保有について非常に示唆に富んだ見解を示しています。教授によれば、すべての企業に当てはまる「最適な」現金保有額というものは存在しません。
ある企業の現金水準が適切かどうかは、1.価値ある投資機会があるか、2.経営陣に規律があるか、そして、3.余った現金を株主に還元する姿勢があるか、という3つの要素で決まるというのです。
つまり、現金は単なる数字ではなく、経営の質そのものを映し出す「リトマス試験紙」だと言えるでしょう。本日はこの視点も踏まえながら、日本企業の現金保有について考えていきたいと思います。
世間の通説:内部留保は“ため込み”か
さて、テレビや新聞で「企業の内部留保が過去最高を更新し、現金を貯め込みすぎている!」といったニュースを一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。賃上げや投資にもっとお金を回すべきだ、という論調で語られることが多いのが特徴です。
書籍:『日本企業はお金持ちになったのか?』
今回のブログで、紹介するのは、企業の現金保有について、膨大なデータ分析で迫った一冊、山田和郎氏の著書『日本企業はお金持ちになったのか? 一現金保有のデータ分析』です。この本は、メディアで語られがちな「企業の現金ため込み」という通説に、学術的な視点から鋭くメスを入れる、非常に知的好奇心を刺激される内容でした。
発見①:現金を増やしているのは中小企業
まず驚かされるのが、現金を増やしているのは、実は大企業よりも中小企業だという事実です。私は「大企業が内部留保を積み上げている」と考えていましたが、データを見ると、総資産に占める現金の割合(現金比率)は、この数十年、大企業ではあまり高まっておらず、むしろ中小企業の方が増加傾向にあるというのです。
発見②:成長企業ほど現金は厚め—“攻めの流動性”
また、成長が期待される企業ほど現金を多く保有するという分析結果は、現金保有=悪という短絡的な見方に再考を迫るものです。これは、M&Aや研究開発投資といった将来の不確実な投資機会を逃さないための資金を確保する合理的な経営判断であり、むしろ攻めの姿勢の表れと捉えることもできます。
通説への疑義:「ため込み批判」は妥当か
こうした事実を踏まえ、著者は「ため込み批判」そのものに疑問を呈します。先行きの見えない経済状況の中で、企業がリスクに備えて現金を厚めに持つことは、むしろ合理的な経営判断とも言えます。何でもかんでも「投資や賃上げに回せ」と批判するのは、企業の置かれた状況を無視した議論になりかねない、というわけです。
会計の基礎:内部留保は現金ではない
そして、本書が最も強く訴えかけているのが、「内部留保は現金ではない」という会計の基本原則です。これは私が過去のブログでも再三取り上げてきたことです。ニュースでは「内部留保が〇〇兆円」と、あたかも企業が金庫に現金を積み上げているかのように報じられますが、これは大きな誤解です。会計上の「内部留保(利益剰余金)」は、企業が過去に稼いだ利益の累計額を示す数字であり、そのお金がすべて現金として残っているわけではありません。工場を建てたり、機械を買ったりと、すでに事業のために使われているものも多く含まれるのです。この点を理解せずに「内部留保に課税しろ」といった議論をすることは、的を射ていない可能性がある、と本書は冷静に指摘しています。
最後に
この他にも、本書では「企業が持つ現金1円は、株主にとって本当に1円の価値があるのか?」を統計的に分析した結果や、株式を新規公開(IPO)したばかりの企業が現金を多く持つ理由など、興味深い論点がありました。この本を読んで改めて感じたのは、データに基づいて物事を多角的に分析し、自分勝手な「思い込み」を疑ってみることの重要性です。イメージや感情論に流されず、事実を正確に捉える力は、ビジネスの世界でも、不可欠なスキルと言えるでしょう。
もし、今回の記事でファイナンスの世界に少しでも興味が湧いた方がいらっしゃいましたら、ぜひファイナンス基礎講座や財務モデリング基礎講座の門を叩いてみてください。数字の裏側にある経済の実態が見えてくると、世界は違って見えるかもしれません。