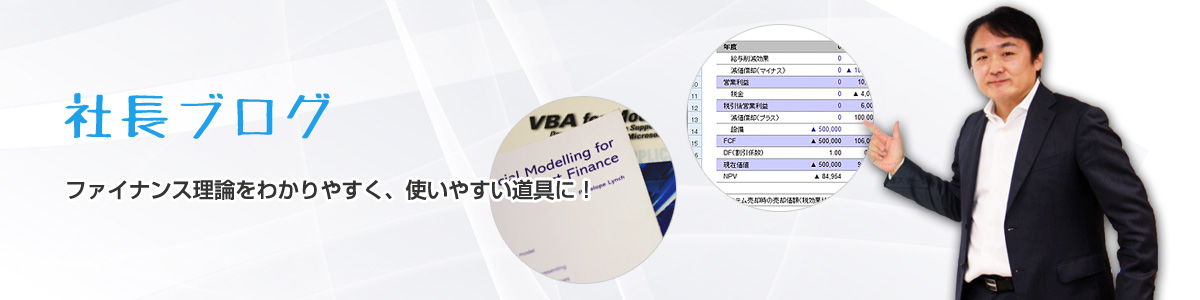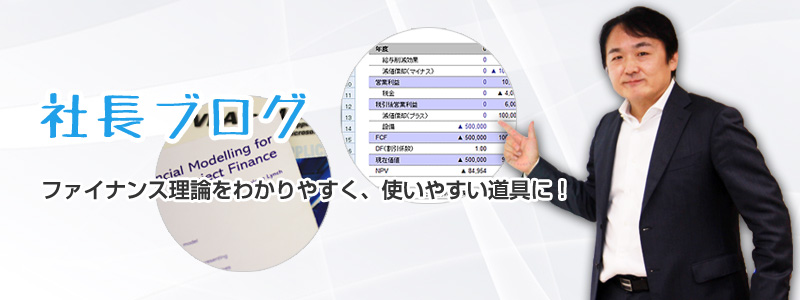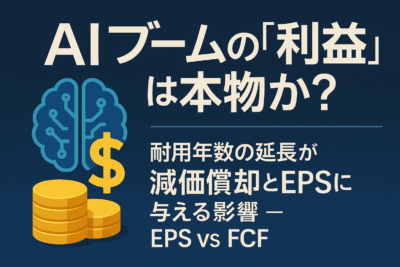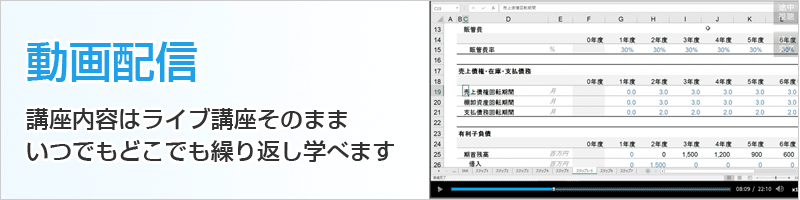AI(人工知能)ブームが世界を席巻しています。エコノミスト誌などの最近の報道によれば、MicrosoftやAlphabet(Google)などの巨大テック企業はAIを追い風に、時価総額が3兆ドル、4兆ドルといった天文学的な領域に達しつつあります。また、今後数年でデータセンターや関連インフラへの投資は累計で数兆ドル規模に達するとの推計が複数示されています。
しかし、この裏で、各社が発表する「利益」の信憑性に疑問を投げかける重要な論点が指摘されています。それは、AI投資に関する「会計処理」です。最大の論点は、AIの頭脳であるNVIDIA製の高価なAIチップなどを搭載した「サーバー(データセンター資産)」の会計上の耐用年数です。
技術革新のスピードは凄まじく、NVIDIAのCEOが新世代(Blackwell)登場で旧世代(Hopper)の価値低下を冗談めかして示唆する場面もありました。これは「旧型の相対価値低下(=陳腐化の速さ)」を示す文脈であり、即座に無価値という趣旨ではありません。
ところが、近年、Microsoft、Alphabet、MetaといったAI大手の多くはこのサーバーの会計上の耐用年数を延長しています。Microsoftは4年から6年へ(FY2023から有効)、Alphabetもサーバーと一部ネットワーク機器を6年へ見直し、2023年通年で減価償却費が約39億ドル減少しています。Metaは5.5年への延長で、2025年に約29億ドルの償却費減見込みと報じられています。
耐用年数を長く設定すると、どうなるでしょうか? 購入した高額なサーバーの費用(取得原価)を、より長い期間にわたって分割して費用計上(=減価償却)することになります。
例: 600億円のサーバー
耐用年数3年 → 年間の減価償却費:200億円
耐用年数6年 → 年間の減価償却費:100億円
つまり、耐用年数を長く設定し直すだけで、年間の費用が減り、その分だけ会計上の「利益」がカサ上げされるのです。
なお、「各社が耐用年数を短く(実態に合わせ)修正したら大手5社の税引前利益が8%=7,800億ドル吹き飛ぶ」とエコノミストの記事にありましたが、実際の開示・報道ベースでは、一社あたり年数十億ドル規模の影響が実際のところです。
ここで、ファイナンスの最も重要な原則に立ち返る必要があります。それは、「会計上の利益」は変わっても、「キャッシュフロー」は原則として変わらないということです。減価償却費は、会計上は費用として計上されますが、実際に現金が出ていくわけではありません(現金はサーバーを「購入した時」にすでに会社の金庫から出て行ってしまっています)。
企業が将来生み出すキャッシュフローの総額は、耐用年数を3年に設定しようが6年に設定しようが、前提が同じなら本質的には変わりません。企業価値を測る指標として「利益」や「EPS(1株当たり利益)」に依存することは危険です。
もし投資家や株式市場がEPSや、EPSから計算されるPER(株価収益率)ばかりを追いかけていれば、経営者は短期的なEPSを良く見せるために、実態の技術陳腐化スピードを無視して会計上の耐用年数を恣意的に(不当に長く)設定するインセンティブに駆られてしまいます。これは、技術の急速な進化という現実から目をそらし、実態よりも「儲かっているように見せかける」行為になりかねません。
私たちが注目すべきは、AIという技術革新が、将来にわたってどれだけ本質的な「フリー・キャッシュフロー(FCF)」を生み出すか、という一点です。会計上の利益(EPS)の増減に一喜一憂するのではなく、その企業がどれだけのキャッシュを生み出す力を持っているのか。ROIC(投下資本利益率)とWACC(加重平均資本コスト)の差、そして維持投資と成長投資がどれくらい必要なのか、見極めることが重要です。それこそが企業価値の本質であり、私たちが常に注目すべきポイントなのです。