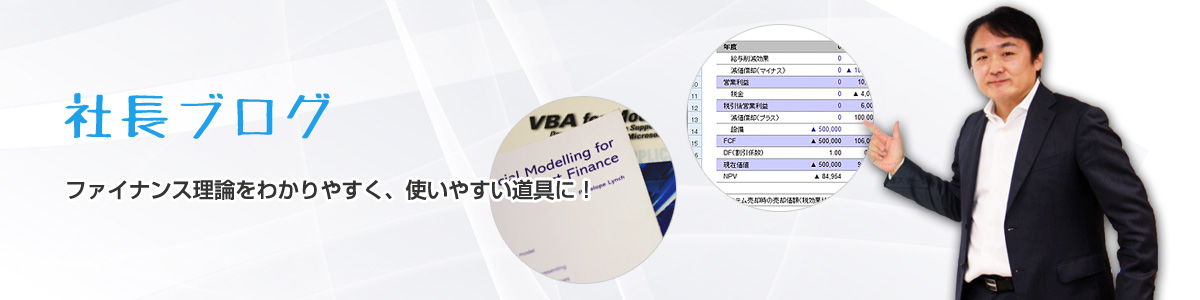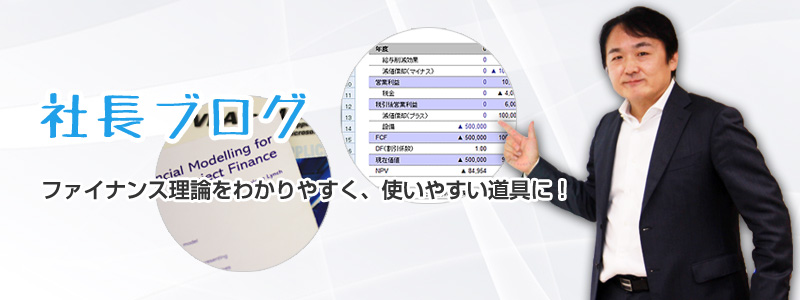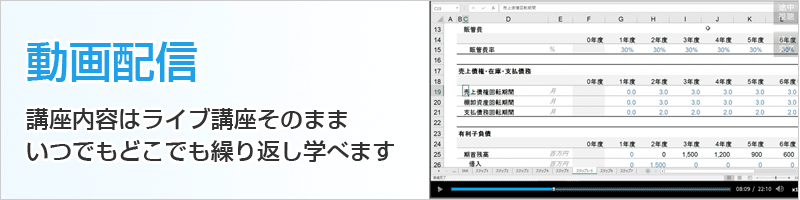前回のブログ「日本金融の新たな挑戦「企業価値担保融資」とは?」では、企業価値担保融資(EVL)が、無形資産を価値の源泉とする現代の企業、特にスタートアップや事業承継に課題を抱える中小企業にとって、いかに大きな「光」となるかを見てきました。しかし、どんな画期的な制度にも、光が強ければ強いほど濃くなる「影」が存在します。
今回は、このEVLに潜む構造的な課題やリスク、すなわち「影」の側面に深く切り込み、この変革を真の成長エンジンとするために乗り越えるべき壁は何かを考察します。
まず目を向けるべきは、融資の担い手である金融機関が直面する、越えるべき巨大な壁です。EVLの成否は、融資の判断基準が「過去の資産」から「未来の事業性」へシフトすることにかかっていますが、これは単なる業務プロセスの変更ではなく、組織文化そのものの変革を迫る挑戦です。
過去の業績の結果である決算書から算出された財務指標をベースに、不動産担保をバッファとして、融資する、しないを判断してきた銀行員のマインドセットが果たして、変わりえるのか。不動産のような明確な時価が存在する資産と異なり、知的財産、ブランド価値、経営チームの能力といった無形資産の価値を客観的かつ定量的に評価することは極めて困難です。
将来キャッシュフローの妥当性を見抜くには、従来と異なるマインドセット、スキルが全ての金融機関で求められる時代になると言えるでしょう。長年、担保・保証を前提とした融資モデルに最適化されてきた組織のスキルセット、人事評価、そしてリスクカルチャーを転換するには、相当な覚悟とコストが伴います。
一方で、企業側もこの新たな制度を手放しで歓迎しているわけではありません。多くの経営者が懸念するのが「経営への過剰な干渉」です。金融機関が融資先の事業内容に深くコミットする「伴走支援」は、有益である半面、債権者という強い立場からの「支配」に転じるリスクをはらみます。
特に、返済が滞った場合の金融機関の発言力は絶大なものとなり、本来株主が持つべき経営のコントロールが侵害される恐れもあります。また、「なぜ、あの会社はあれだけの融資を受けられるのか」といった不満や疑念を生まないためにも、評価プロセスの透明性と、金融機関側の十分な説明責任が不可欠となります。
最後に、制度そのものが内包する、よりマクロな視点でのリスクも忘れてはなりません。債務不履行時の出口戦略として「原則M&A」が想定されていますが、これは適切な買い手がタイムリーに存在して初めて成立する話です。
景気後退局面やニッチな市場では買い手探しが難航し、結果として事業価値が毀損された価格での「叩き売り」に至る懸念は拭えません。また、専門的かつ公正な管理を担うとされる「企業価値担保権信託会社」が、多様な事業性を評価し、巨大な金融機関を相手に中立性を保てるのか、その実効性はまだ未知数です。
ここまで見てきた様々な「影」は、制度の欠陥というよりも、その運用を成功させるための「挑戦」と捉えるべきでしょう。この挑戦を乗り越えるには、金融機関の自己変革、企業側の積極的な情報開示、そして社会全体のM&A市場の活性化が不可欠です。ただ、このことは、私が銀行員だった30年近く前からわかっていたことなのです。
いずれの立場であれ、問われるのは『事業の本質を見抜く力』です。ご自身が銀行員であったならば、考えていただきたいです。この歴史的な転換点を、自身のキャリアを飛躍させる好機と捉えるのか。そのために、あなたは明日から何を学び、どう行動するのでしょうか。